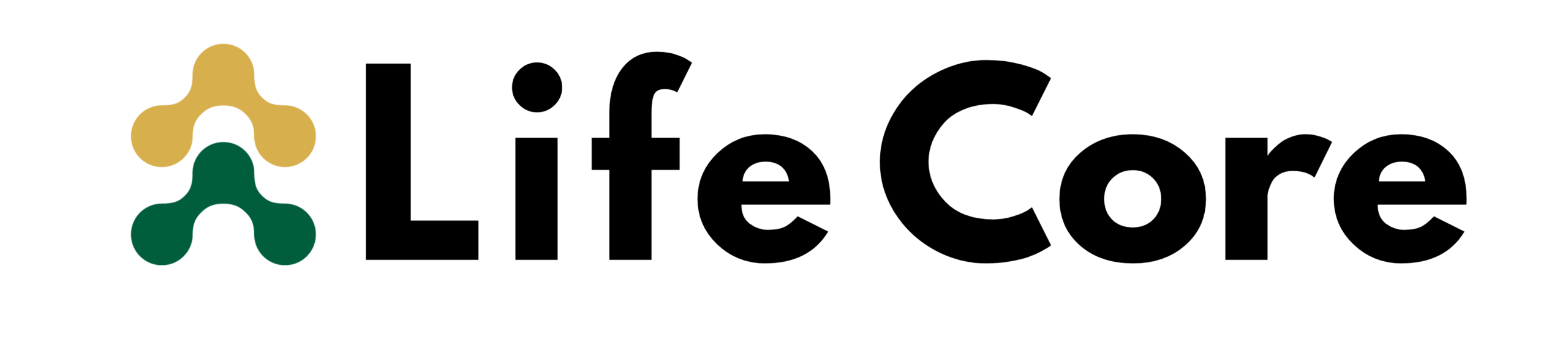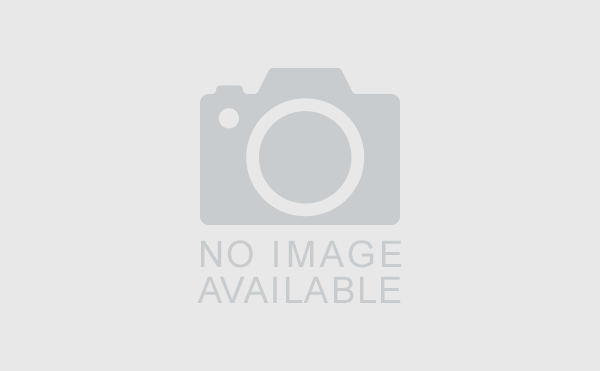【健康コラム 15 】骨を丈夫に保つ生活習慣!転倒しにくい体づくり
① 骨量が減る仕組みと早めの対策
どうして骨が減るの?
- 骨は「壊す」「作る」を繰り返す組織です。年齢や運動不足、栄養不足、女性では閉経に伴うホルモン変化などで“作る力”が弱くなり、結果的に骨の量が減ります。
- 骨が薄くなると、ちょっとした転倒で骨折しやすくなります。特に大腿骨(股関節周り)や腕の骨、背骨がリスク部位です。
いつから対策を始めるべき?
- 若いうちからの生活習慣が将来の骨の基礎になりますが、40代以降は特に注意が必要です。閉経後の女性は骨量の減少が早くなるため、早めに取り組みましょう。
- 既に骨粗しょう症の診断がある方は、医師の治療(薬物療法)と併せて運動・栄養・環境整備を行うことが大切です。
② 食事で骨の“材料”を確保する
重要な栄養素と役割
- カルシウム:骨の主要な材料。毎日の食事でこまめに摂ること。
- ビタミンD:カルシウムの吸収を助ける。食事+日光で補う。
- たんぱく質:骨の“骨基質”(たんぱく質のネット)を作る上で必須。
- ビタミンK、マグネシウム、ビタミンC:骨の質を保つ補助的栄養素。
実践しやすい食品例(朝・昼・夜の組合せ)
- 朝:牛乳またはヨーグルト+納豆トースト(カルシウム+たんぱく質)
- 昼:鮭の塩焼き+きのこ入り味噌汁+小松菜のおひたし(ビタミンD、カルシウム、ビタミンK)
- 夜:豆腐と野菜の煮物+小魚(しらす・煮干し)を副菜に(カルシウム強化)
食べ方のコツ
- カルシウムは一度に大量に摂るより、数回に分けて摂ると吸収が良くなります。
- たんぱく質は“1食に均等に”分散して摂りましょう(朝・昼・夜それぞれで20g前後目安に)。
- サプリを利用する場合は、医師・薬剤師に相談しましょう。薬との相互作用や過剰摂取に注意です。
③ 日光とビタミンDの実践
どれくらい日光を浴びればよい?
- 一般には、顔や手などを毎日短時間(目安:15分〜30分程度)日光に当てることで体内でビタミンDが合成されます。季節・肌の色・年齢で差があるため、目安です。
- 午前中〜昼前の散歩や夕方の短時間外出を日常に取り入れると続けやすいです。
注意点(皮膚が弱い方/紫外線対策)
- 日焼けを避けたい場合は、日光時間を短くして頻度を増やす、または顔だけでなく手や腕を出す程度にするなど調整しましょう。
- 紫外線が強い時間帯は日焼けリスクが上がるため、医師や皮膚科の指示のもとで時間調整してください。サンスクリーンを塗ってしまうとビタミンD合成が阻害されるため、合成を目的とする短時間はクリームなしで行う方が効率的です(ただし皮膚が弱い方は専門家に相談を)。
食事でのビタミンD補給
- 魚(鮭、サンマ、イワシ、サバ)やきのこ類に多く含まれます。日光が十分でない季節や屋内中心の生活では食事で補うことを意識しましょう。
④ 骨に効く“負荷”のかけ方と安全な運動プログラム
骨はどんな刺激に強く反応する?
- 骨は重力や筋肉が骨を引っぱる力など“力のかかる刺激”に反応して強くなります。重要なのは「繰り返し」「定期的に」「日常より少しだけ負荷を上げる」こと。
具体的な家庭でできる運動
各運動は週に3〜5回を目標に。無理のない範囲で行い、痛みが出たら中止し医師へ相談しましょう。
- 立ち上がりスクワット(椅子サポート)
- 回数:1セット8〜12回、2〜3セット。
- 方法:椅子に座った状態からゆっくり立ち上がる。初めは両手で椅子の肘掛けやテーブルを支えてOK。徐々に手を使わずに行いましょう。
- 効果:大腿部と骨盤周りに負荷が入り、下肢骨の刺激になります。
- かかと上げ(ふくらはぎ強化)
- 回数:1セット10〜15回、2〜3セット。朝晩に実施。
- 方法:立った状態で両手を壁や椅子の背にもたれて、つま先立ちをゆっくり行いましょう。
- 効果:足首・下腿骨へ負荷。転倒予防にも有効です。
- バランストレーニング(片脚立ち)
- 回数:左右それぞれ30秒〜1分、2セット。
- 方法:安定した椅子や手すりのそばで片脚で立つ。最初は10秒を目標に。慣れてきたら目を閉じる・クッション上で行うなど難易度上げましょう。
- 効果:筋力だけでなく姿勢保持機能が向上し転倒リスク低下が期待できます。
- 有酸素運動(ウォーキング)
- 目安:1回20〜30分、週3〜5回。
- 効果:骨に一定の衝撃を与え、心肺機能・筋力も同時に鍛えることが出来ます。
運動強度の上げ方(進め方)
- 2〜4週間ごとに回数やセット数を少し増やす(例:10回→12回)。
- 安全のため、最初は理学療法士や運動指導者にフォームを見てもらうことが望ましいです。
⑤ 転ばない工夫(環境整備+補助具+生活習慣)
家庭内の危険箇所チェックリスト
- 床の段差、たたみとフローリングの境目、敷物の端でつまずきやすい。
- 電気コード・荷物・脱ぎっぱなしの靴が散らかっていないか。
- 浴室など滑りやすい場所に滑り止めマットや手すりがあるか。
- 夜間の移動経路に足元灯を設置しておく(消し忘れに注意)。
補助具の活用
- 必要であれば杖や歩行器を使うことは“弱さの証”ではなく安全対策です。正しい長さや使い方は専門家に確認してください。
- 滑りにくい底の靴・室内履きを選ぶ。靴が合わないと歩行が不安定になります。
日常での習慣改善
- 荷物を両手で持つとバランスを崩しやすいので、肩掛けバッグや片手に重い荷物は避ける。
- 疲れている時・薬の副作用がある時は長距離の移動を控える。
- 視力が低下している場合は眼科受診を。視力低下は転倒リスクと直結します。
🔎 チェックポイント(いつ医師に相談するか)
- 背中が曲がってきた、身長が縮んだ(過去数年で数センチ縮んだ)と感じる場合。
- 転倒で痛みが長引く・動けないなどの症状があるとき。
- 骨折の既往がある、家族に骨粗しょう症の人がいる、長期間ステロイドを使っている等のリスクがある場合。
→ これらは医師に相談し、必要なら骨密度検査や薬物療法について話を聞きましょう。
よくある疑問(Q&A)
Q:サプリでカルシウムを摂ったほうが良い?
A:食事で十分摂れない場合は有用ですが、過剰摂取や薬との相互作用があるため、医師や薬剤師と相談してください。
Q:高齢でも筋トレは効果がありますか?
A:はい。適切な負荷で安全に行えば筋力も骨も改善します。最初は専門家の指導を受けると安心です。
Q:骨折歴がある場合の運動は?
A:骨折部位や治癒状況により運動内容が変わります。必ず担当医・理学療法士と相談して開始してください。
最後にひとこと
骨を守る対策は「薬だけ」でも「運動だけ」でも不十分です。
日々の食事・日光・運動・住環境をバランスよく整えることが、将来の自分を守る最も現実的で有効な方法です。小さな変化を積み重ねていけば、転倒しにくい・動きやすい体に近づきます。